10年前のドローン
最近はすっかり利用しなくなったAmazonの購入履歴を調べてみると、私がドローンを買ったのはちょうど10年前です。通販の罠で、思っていた以上に大きくて電車やチャリで気軽に運べるサイズではありませんでした。結局、5~6回飛ばしただけで数年前に廃棄しました。
当時はまだ法整備されていませんでしたが、とりあえず航空法を調べたのを覚えています。空港から何キロ以内の基準が空港の敷地なのか、滑走路なのか、事務所なのかわかりませんでした。調布飛行場でも滑走路は800mあります。敷地はもっと広いわけです。
主に河川敷で飛ばしただけですが、少なくとも当時の法令には抵触していないはずです。人や民家はもちろん、線路に落としてもアウトですし電線も避けなければなりません。暑かったり寒かったりするのも一緒に外出したくない理由になります。
で、今回初めて気づいたことです。空港には「標点」と呼ばれる基準点があるようです。
飛行場を代表する地点で多くの場合飛行場の地理的中心となる地点付近に定められ、公共用飛行場については空港の付帯データーとして緯度経度により公示されている標点のことをいう。
SKYART JAPAN>飛行場標点とは何か??
おそらくこの「標点」基準で考えればよかったものと思われます。そして、もう1つ抱えていた疑問も解消に向かっています。
空港気象観測所の緯度経度
空港内に設置されているアメダス観測所の緯度経度をGoogle Mapや地理院地図で検索すると、滑走路の中央付近にピンが刺さるケースが多いことに私は気づいていました。宮崎空港のアメダス赤江です。

稚内空港のアメダス声問です。北に若干ズラせば滑走路中央になります。

福島空港のアメダス玉川です。東にズラせば滑走路中央です。

観測露場や空港事務所を示した緯度経度でないことは明らかです。
幾何学的重心
アメダス観測所の緯度経度でマップ検索した場合、示されるピン(黄色)の北または東に実際の観測露場(ピンク)があります。その差異は最大でも200m以内です。

これを自分なりに脳内補正して、地方空港の場合は滑走路の中央部分が示されているように感じていました。
飛行場には標点というものがあります。その飛行場の標点は着陸帯の幾何学的重心となっています。
Alpha Aviation co, ltd>航空豆知識「飛行場標点と標高について」
この「幾何学的重心」に大いに納得する次第です。滑走路が1本だけの場合は、自動的に滑走路の中央になるからです。
というわけで、空港気象観測所について気象庁が示している緯度経度は「着陸帯の幾何学的重心」である「標点」が採用されているようです。おそらく歴史的な経緯もあってのことと推測されます。

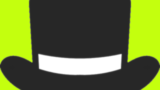



コメント